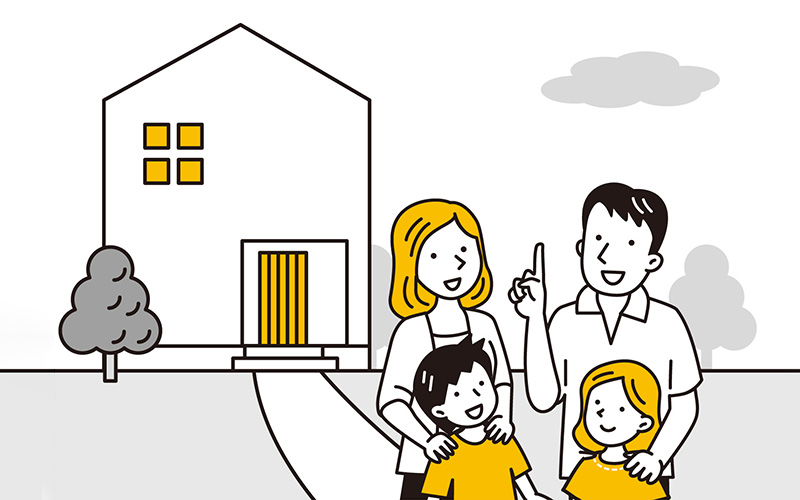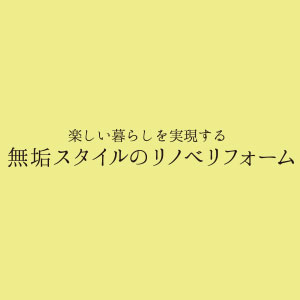世界最古の木造建築、伝統工法の耐震性は?
2006.01.18 Wed
今日、お客様と木造建築の話をしていて、一番古い木造建築は? 伝統工法の耐震性は?
という話になったのですが、世界最古の木造建築物は、皆さんご存知だと思いますが、法隆寺の五重塔です。
でも、この五重塔は、現在、伝統工法と一般に言っているものと、構造が異なります。
一般に伝統工法と言われる、貫工法は実は鎌倉時代に中国から伝わってきたもので、先にあげた建物
には使用されていない工法です。
かといって、耐震性がないというわけではなく、世界最古という歴史がしめすように法隆寺の五重塔のような飛鳥様式では、木の摩擦力によって発生する熱エネルギーに地震エネルギーを変換してしまうということと、よく「しなる」という木の性質を利用して持たせています。
後の校倉造やログハウスなどもこの部類に入ります。
現在、一般的にいう伝統建築の貫工法では、柱の中を貫が貫通することにより、支点の数を増やし、そこから地震のエネルギーを逃がしてしまうというものです。
また、世界最大の木造建築物といわれる、東大寺の金堂はどうなっているでしょう。
現在のものは1707年に再建されたものですが、驚くべきことに柱に集成材?が使われています。
現在の集成材の定義とは違いますが、ドイツで20世紀のはじめに考え出されるより、ずっと以前に使われているのには、感心を通り越し感動すら覚えてしまいます。
また、明治36年の修復の際には、なんと鉄骨も使用しています。
昔の建物の話ばかりしてきましたが、現在の木造はどうなっているかというと、筋交いと呼ばれるつっかえ棒で支える工法・2×4工法のように「面」で持たせる工法など、多種多様です。
耐震性が全てではないですが、家づくりを考えるとき、決して無視できるものではありません。
自分にあった家作りのなかに、耐震性は絶対に考慮してください。